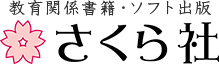【横山験也のちょっと一休み】№.3771
分数のたし算の話を一つしましょう。
2/4と1/4を足すと3/4になります。
分子だけを足して、分母は足しません。
でも、どうして分母は足してはいけないのでしょう。
説明の仕方は、いろいろとあるのですが、今回は、私の好きなビーカーを使っての説明をお話ししましょう。
どのように説明するかというと、「メモリは足せないでしょ!」が主眼となります。
一方のビーカーに水を半分入れ、メモリをつけます。
もう一方のビーカーには、水を1/4だけ入れて、こちらにもメモリをつけます。
 そうして、子供たちの前で、1/4の水を1/2のビーカーに移します。
そうして、子供たちの前で、1/4の水を1/2のビーカーに移します。
水は足した。しかし、メモリはそのまま。
これが、分母を足さない理由となります。
分母を足してはいけない理由を説明するときに、効果的なのは、分母という用語からいったん離れることです。
子供たちのよく知っている何か別のものに例えて話を進めるようにしていきます。それが、私の場合、ビーカーのメモリでした。
ビーカーのガラス面のメモリは水があろうが無かろうが、水をどこかに移しても、常にそのままです。だから、足し算も引き算もできません。
見ればわかることなので、そこから、メモリは分母なので、分母はメモリと同様とつながり、頭にすっきりと入っていきます。この見ればわかるという感覚の世界を実現することは、案外重要です。
また、別の見方をすると、分子は中身、分母はメモリとも、伝わります。これによってよりたし算されているのは、中身の水だけなのだと、一層説明がしやすくなります。
こういう説明は論理的説明とは少し異なります。
どちらかといえば、感覚的説明、直感的説明に近いです。
これが案外重要だというようなことが、数学の一般書を読んでいたら書いてありました。
そこではメタファーという用語で説明されていました。心理学用語でしょうか。そういう言葉をすでに学んでいる先生には、分母をメタファーして説明していますといった方が伝わりがいいかもしれません。
まあ、私は日本人なのでメタファーだと通じにくいので、分母を比喩ってると言っています。
感覚的説明をどう加えていくか。これは教師の知恵の出しどころです。
—
下の3冊は、私が書いた算数のアイディア教材集です。どれも面白いです!
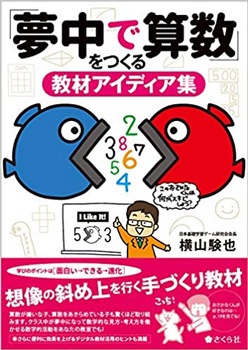 |
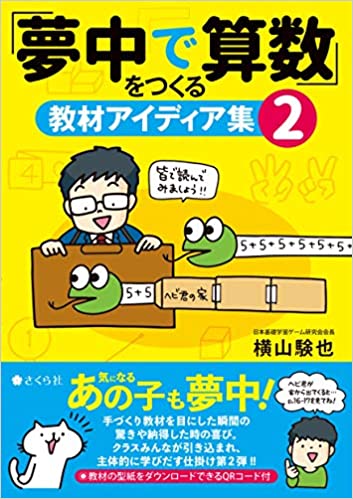 |
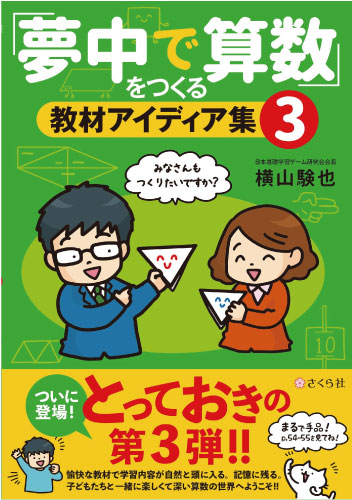 |