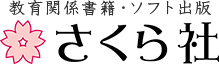【横山験也のちょっと一休み】№.3771
今日は、ちょっと珍しい、引き算の筆算の話をしましょう。
引き算の筆算の厄介な点は、繰り下がりにあります。
うっかりすると、計算ミスをしてしまうので、通常は下のように書いて計算していきます。
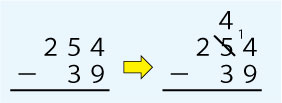
一の位の引き算がすぐにはできないので、十の位から1繰り下げてきます。
何も書かずに計算すると、十の位でうっかりすることが起こりかねません。
ですので、繰り下げたことを忘れ無いようにきちんと書いていきます。
そうして、一の位の計算が終わったら、十の位では「4-3」を計算します。
大正時代の本に、このやり方とはちょっと違う、なるほどと思えるやり方が載っています。
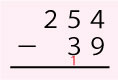
繰り下がりの1に対応する数を、ちょっと目立つように、ここでは赤で書いておきました。
見慣れないところに1が書かれていますが、少し考えれば、やり方が伝わってきます。
十の位は、「5-3-1」と計算しているのです。
一の位が引けない場合、「14-9」を計算します。これは慣れてしまえば、何も書かなくてもできます。
でも、繰り下げた1は、うっかりすると忘れることがあるので、それを「5-1」とせずに、「5-3-1」としています。一気に引き算をしています。
なかなかの妙案!と伝わってきます。
昔は、こういう計算をより簡単に素早く、それでいて正確にできる方法を何とか見つけ出して・・・と考える先生がけっこういました。この筆算を考え付いた先生も、きっとそういう先生だったように思います。
なかなかいい方法と感じるのですが、初心者にはちょっと向きません。
たぶん、筆算に慣れてきた子に、こういうのもあるよと伝える分にはいいかもしれません。
なぜ、そう思うのか。
普通の筆算は、具体的イメージの通りの手順になっています。
しかし、大正時代のこの方法は、具体的イメージで考えるとちょっと複雑になっているからです。
具体的イメージというのは、先生が子供たちに話すような世界です。
4から9は引けないね。
だから、となりの5から1借りてきて、その1は一の位では10になるので、14-9を計算します。
5は1貸してあげているので、4になっています。
だから、十の位は4-3になります。
この話の順番に斜線を引いたり、1を書いたりします。
流れる通りの記述です。
ですが、大正時代のこのやり方は、このイメージ通りの流れになりません。
4から9は引けないね。
だから、となりの5から1借りてきて、その1は一の位では10になるので、14-9を計算します。
ここまでは、同じです。
問題はその次です。
5から1借りたけど、その1はすぐには引かないで、5から3を引くときに、ついでに1も引いていきます。
借りたことを一時保留しています。そうして、後からまとめて引く、という手順が具体的イメージとしてなかり高度となります。
ですので、習い始めの子にはこの方法はちょっと向かないと思えてきます。
ですが、慣れてきたら、こういうやり方もあるということを話すのもいいですね。
このやり方が載っていたのは『どうすれば算術が上手になるか』(近藤精一著、門部書店)です。
昔の本ですが、私の時代に無い考え方が載っているので、実に面白く感じます。
—
下の3冊は、私が書いた算数のアイディア教材集です。どれも面白いです!
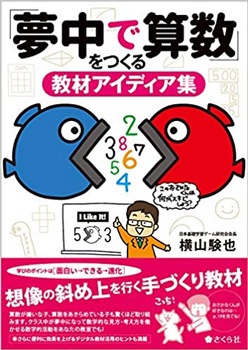 |
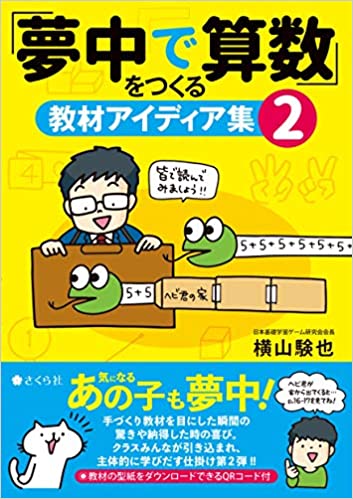 |
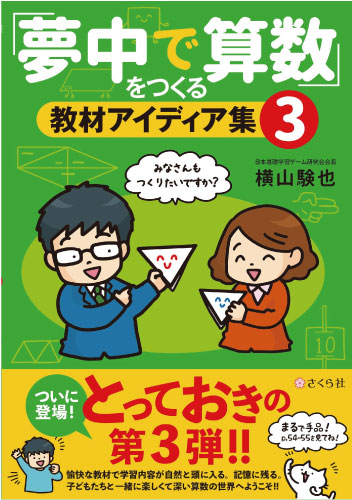 |