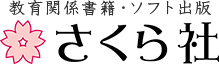【横山験也のちょっと一休み】№.3774
城ケ崎先生とお茶をしたときのことです。私は何も持たずに行ったのですが、城ケ崎先生はレポートを持ってきていました。
これには、さすがと思い、何かしらの話を・・・と思いました。
そのレポートには学校での出来事が書かれていたのですが、その最後に指導の背景に関わることが書かれていました。
こういうバックボーンを示すのですから、相応の心酔状態にあることがわかります。そういう思考のよりどころがあることは、実に有益なことです。
そこに書かれていたことは「儒教」についてでした。儒教はこういう教えなのですと。
儒教の話をすると、「それは宗教では?」と思う先生もいるのですが、そういう先生に「先生、宗教ってなんでしょうか。宗教と宗教でないものの違いを聞かせてもらえますか」と話しかけると、たいていはここで話が終わります。
多分、「〇〇教」となっているから、宗教と思ったのだろうと思います。これは、致し方のないことです。「教」の字が通じているからです。
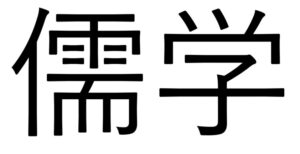 それを嫌ってか、昔から「儒学」という呼び方もされていました。私も「儒学」という言葉の方が好きなのですが、儒教もよく用います。
それを嫌ってか、昔から「儒学」という呼び方もされていました。私も「儒学」という言葉の方が好きなのですが、儒教もよく用います。
宗教は、死後の世界を認識して、現生をよりよく生きるように導く教えです。
キリスト教なら、天国という世界を認識します。死後、天国に行けるように、生ある今をよりよく生きようとします。
同様に、仏教でしたら、極楽という世界を認識し、そこへ向かうよう今を生きます。
儒教が宗教でないという大きな理由は、死後の世界を想定していないことです。生きている今のこともよくわからないことだらけなのに、死んでからの世界はさらにわからないとなります。
では、儒教は何なんだ、となります。「儒」の漢字に「雨」があるように、これは潤いです。互いが殺伐となる状態は、ある意味乾燥している状態で、火が立ちやすいです。しかし、互いが潤いを持つようにしていると、いやなことがあっても、水として流れていきます。
こんなとりとめのない話ですが、教育のレポートを端に楽しむことができました。似たような本を読んできた友との語らいはやはり楽しいですね。
—
算数の楽しいアイディア教材でしたら、こちらの3冊も楽しいです。
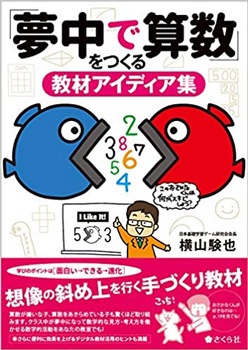 |
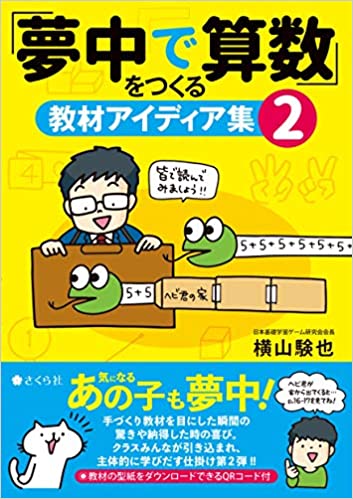 |
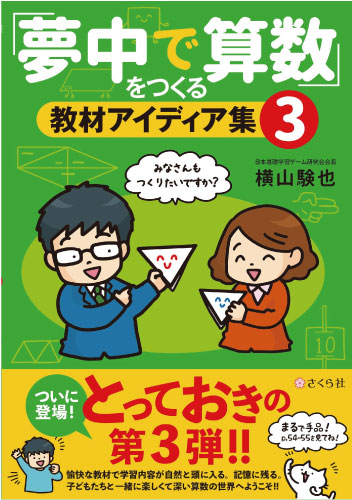 |