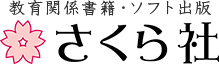【横山験也のちょっと一休み】№.3641
 この写真は「四捨五入ヘビ君」です。
この写真は「四捨五入ヘビ君」です。
4年生の四捨五入の勉強の時に活躍をしてくれます。
「四捨五入」になぜ「へび」が出てくるのでしょうか。その必要性は全くありません。ですから、ほぼ無駄と思えます。
ところが、ところが。
四捨五入にヘビが付け足されて出てくると、子ども達は嬉々と喜んでくれます。5以上と4以下の間に、切込みが入っているので、視覚的にも四捨五入の意味が伝わってきます。
面白いのは、ちょっとした演出ができることです。
 左のように、上半分を前に倒した状態が「五入」の状態となります。一つ前(上)の位に数が入るという意味も持たせることができます。
左のように、上半分を前に倒した状態が「五入」の状態となります。一つ前(上)の位に数が入るという意味も持たせることができます。
逆に、4以下を下にだらりとさせると、捨てられた感が出て、その位はそのままとなります。
こういった演出まではしなくても、小さな細長い紙を子ども達に配り、そこに0から9までの数を書かせて、「マイ四捨へび」を作るのもいいです。四捨五入する数の上に、それを置いてから四捨五入をします。四捨五入がかなりインプットされます。
四捨五入ヘビ君をSNSにアップしたら、アドラー心理学で有名な赤坂真二先生からかきこみがありました。
「講座で先生から直接いただき,すぐに教室で,マイ四捨ヘビくんを全員が作って活用していました♪テストの平均点がグッとアップしました??ありがとうございました。」
ノーベル賞のダニエル・カーネマンの心理学に模して説明すると、四捨五入にへびをあしらったことで、子ども達の「システム1(直感の脳)」が刺激され、そこに意味を持たせたくなり「システム2(考える脳)」が起動し、学習が頭にどんどん入るということです。ヘビが出てこないと、システム2がなかなか起動しない子がいるということです。こういうシステム1を刺激する工夫が大切ということです。
パチンコ風に説明すると、パチンコ台に四捨五入ヘビ君を近づけたら、台がびっくりしてチューリップが全部開いてしまい、学習という名の玉がじゃらじゃら頭に入るようになったということです。
なお、へびのしっぽが上にはねているのは、アブドーラ・ザ・ブッチャーの凶器靴をあしらっているという説もあります。
四捨五入ヘビ君は、下の1巻(白い本)に載っています。
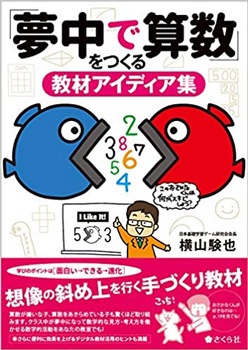 |
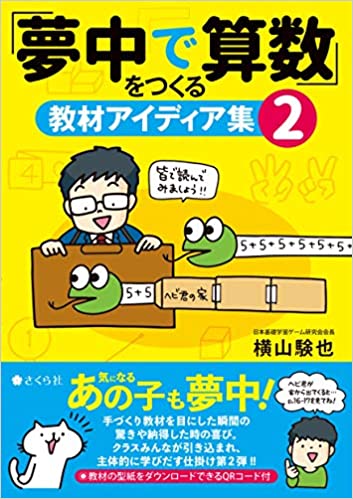 |
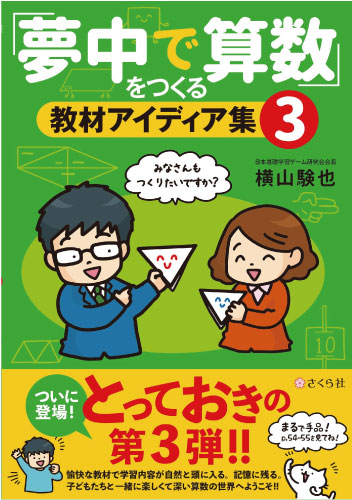 |