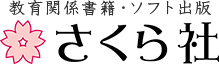松尾英明
まつお ひであき
千葉県公立小学校教諭。
「クラス会議」を中心とした自治的学級づくりを実践し、子どもたち自身が学級運営に主体的に関わる環境を育むことに力を注いでいる。千葉大学教育学部附属小学校特活部にてその手法を研究し、さらに教育心理学を専攻しながら、チーム担任制や教科担任制の在り方について千葉大学大学院教育学研究科で学びを深めた。
現場での豊富な実践経験をもとに、単行本や雑誌の執筆をはじめ、全国各地で教員や保護者を対象としたセミナー・研修会の講師として活動。著書『不親切教師のススメ』(さくら社・2022)では、学校教育の当たり前を問い直し、大きな反響を呼んだ。その主張は各種新聞やテレビメディアでも取り上げられ、広く議論を巻き起こした。近著に『学級経営がラクになる!聞き上手なクラスのつくり方』(学陽書房・2023)がある。
『プレジデントオンライン』『みんなの教育技術』『こどもまなびラボ』『AERA with Kids』などで執筆活動を展開。メルマガ『二十代で身に付けたい!教育観と仕事術』では「2014 まぐまぐ大賞」教育部門大賞を受賞し、2024 年まで部門連続受賞を果たす。
「教育を、志事にする」という哲学のもと、学級自治の可能性を広げる実践を積み重ねながら、子どもたちが主体的に学び、成長できる環境づくりに取り組んでいる。
日本学級経営学会所属。学級づくり修養会HOPE 主宰。
河村茂雄
かわむら しげお
早稲田大学 教育・総合科学学術院 教授 博士(心理学)
筑波大学大学院教育研究科カウンセリング専攻修了。公立学校教諭・教育相談員を経験し、岩手大学助教授、都留文科大学大学院教授を経て、現職。日本学級経営心理学会理事長、日本教育カウンセリング学会理事長、日本教育心理学会理事長、日本教育カウンセラー協会岩手県支部長。公認心理師、臨床心理士、学校心理士スーパーバイザー。
『子どもたちの行動を決める学級の「空気」』『子どもの非認知能力を育成する 教師のためのソーシャル・スキル』『アクティブラーニングを成功させる学級づくり』(以上 誠信書房)、『ピアフィードバックのゼロ段階』『日本の学級集団と学級経営』『学級集団づくりのゼロ段階』『大人になるための非認知能力』(以上 図書文化)、『教師のための失敗しない保護者対応の鉄則』(学陽書房)、『講師のための学級経営コンサルテーション・ガイド』『学級集団づくり/学級崩壊の変遷』『アクティブラーニングを推進する学習集団/学級集団づくりのためのアンケート WEBQU―解説書―』(以上 WEBQU 教育サポート)
苫野 一徳
とまの いっとく
教育哲学者・熊本大学 准教授
永井初男
ながい はつお
広島県安芸高田市教育委員会 前教育長
西門隆博
にしもん たかひろ
兵庫県川西市立多田小学校 校長
高橋幸夫
たかはし ゆきお
愛知県名古屋市立香流中学校 校長(同市立八幡中学校 前校長)
中西 茂
なかにし しげる
教育ジャーナリスト、星槎大学 客員教授、千葉県松戸市教育委員(NPO法人共育の杜 理事)
池田久美子
いけだ くみこ
東京生まれ。
1974年東京教育大学教育学部教育学科卒業。
1978年東京大学大学院 教育学研究科修士課程終了。
1981年慶應義塾大学大学院社会学研究科博士課程単 位修得満期退学。
信州豊南短期大学教授、三育学院大学講師を務めた。専攻は教育哲学、国語教育。 2019年没。
宇佐美 寛
うさみ ひろし
千葉大学名誉教授(教育学博士)
1934年神奈川県横須賀市生まれ。東京教育大学教育学部卒業、同大学大学院教育学研究科博士課程修了。
東京教育大学助手、千葉大学講師、同助教授、教授(1993-97年教育学部長、1998-2000年東京学芸大学教授併任)。
1961~62年米国、州立ミネソタ大学大学院留学(教育史・教育哲学専攻)。
九州大学、山梨大学、岩手大学、山形大学、秋田大学、茨城大学、上智大学、立教大学、早稲田大学等の非常勤講師(客員教授)を務めた。2023年没。
三井一希
みつい かずき
山梨大学教育学部・准教授
1982年山梨県北杜市生まれ。熊本大学大学院教授システム学専攻修了、博士(学術)。山梨県公立小学校・教諭、台北日本人学校(台湾)・教諭、常葉大学教育学部・専任講師を経て、2022年より現職。 文部科学省「GIGAスクール構想に基づく1人1台端末の円滑な利活用に関する調査協力者会議」委員、同学校DX戦略アドバイザー、デジタル庁デジタル推進委員、日本教育工学協会理事,東京教育研 究所主任研究員などを歴任。令和6年度発行 小学校教科書(算数、理科、生活)編集協力者、令和7年度発行中学校教科書(数学、技術・家庭)編集協力者。文部科学省「情報活用能力調査」作問委員。
著書に『1人1台端末活用パーフェクトQ&A』(明治図書)、『小学校低学年1人1台端末を活用した授業実践ガイド』(東京書籍)など
佐藤和紀
さとう かずのり
信州大学教育学部・准教授
1980年長野県軽井沢生まれ。東北大学大学院情報科学研究科修了、博士(情報科学)。東京都公立小学校・主任教諭、常葉大学教育学部・専任講師等を経て、2020年より現職。文部科学省教育の情報化に関する手引執筆協力者、同「GIGA スクール構想に基づく1人1台端末の円滑な利活用に関する調査協力者会議」委員、同ICT活用教育アドバイザー等を歴任。2021年より日本教育工学会・代議員、2023年よりNITS独立行政法人教職員支援機構・フェロー。
著書に『情報社会を支える教師になるための教育の方法と技術』(三省堂)、『1人1台端末活用パーフェクトQ&A』(明治図書)、『ICT 活用の理論と実践:DX時代の教師をめざして』(北大路書房)など
堀田龍也
ほりた たつや
東京学芸大学教職大学院・教授、同学長特別補佐
文部科学省・視学委員
国立教育政策研究所・上席フェロー
信州大学・特任教授
1964年熊本県天草生まれ。東京学芸大学教育学部卒業。博士(工学)(東京工業大学)。東京都公立小学校・教諭、富山大学教育学部や静岡大学情報学部・助教授、メディア教育開発センター・准教授、玉川大学教職大学院・教授。文部科学省・参与、東北大学大学院情報科学研究科・教授等を経て、2024年より現職。中央教育審議会・委員、同デジタル学習基盤特別委員会・委員長等を歴任。2021年より日本教育工学会・会長。 著書に『学校アップデート』(さくら社)、『情報社会を支える教師になるための教育の方法と技術』(三省堂)、『クラウドで育てる次世代型情報活用能力』(小学館)など
八木澤 史子
やぎさわ ふみこ
千葉大学教育学部・助教
1978年広島県広島市生まれ。東北大学大学院情報科学研究科博士後期課程修了、博士(情報科学)。 広島市・広島県・東京都の公立小学校教員を経て、2022年4年より現職。(公財)教科書研究センター「授業における教科書の使い方に関する調査研究」委員、同センター特別研究員、日本教育工学協会理事。
著書に『情報社会を支える教師になるための教育の方法と技術』(共著、三省堂)、『GIGAスクール はじめて日記4』(共著、さくら社)など。
瀬戸SOLAN学園 初等部
2021年愛知県瀬戸市に株式会社立の小学校として開校。2023年に愛知県より学校法人の許可を得る。
2025年度4月には中等部が開校する。
建学の精神は、「グローバルシチズンシップの育成」。日本語や英語などの言語を駆使して多様な立場の人々と議論し合い、自らの意思によって持続可能な世界を築き上げる人材を育てようと自立・自律した学習者の育成を目指している。そのため、個人探究を軸に、英語教育や情報教育に力を入れている。現在は、1年生から6年生まで、321名の児童が在籍し、60名の日本人教師と外国人教師で指導にあたっている(2024年12月31日現在)。
ひぐち きょうこ
樋口 匡子
埼玉県生まれ
画家・イラストレーター
武蔵野美術大学短期大学部 空間演出デザイン科 専攻科卒業。
1996年東京・有明での個展をはじめ、1997年ひとつぼ坪展入選、2001年チェコ・プラハでの2人展、2002年新風舎第4回絵本のコンクール入選ほか、近年では鳥をテーマに2023年東京、2024年石川・金沢での個展など、作品制作の傍ら全国各地で作品展示を開催する一方、装画やイラストなども手がける。現在金沢市在住。絵本はかつて絵画教室で子どもたちと過ごした経験から生まれたこの作品が初めて。